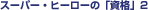
「オレは正義の味方になんかなりたくない!」
――ってのは、『ムーン・ライティング』シリーズの2作め、『お月様の贈り物』でD・Dが言い出す話。つまり彼が『スパイダーマン』のマンガを読んでたら、ヒーローが自分でコスチュームを風呂場で洗濯してるシーンに出くわして、ひどく可哀想だと思った、と。でもスーパー・ヒーローは識別のためにも派手な服を着なきゃならない、でもクリーニングなんかに出して正体をバラすわけにはいかない、と。だから「オレは正義の味方になんかなりたくない!」…ってな理路だと、たぶん思われる。「狼男」の血をひょんなことから受け継いでしまった時点でのD・Dの第一声がコレだったのだ。いやそれより治癒能力や運動能力が飛躍的に向上した今、公園で女性の悲鳴を聞いたり火事で逃げおくれた人がいるなんて現場に出くわしたら……ってな「お人好し」な彼の将来を先取りした想定は、腐れ縁の親友にして真正の「狼男」の血を引くトマスの「だからって(他人より秀でた能力を持ったからって)……何故助けなきゃならない?」ってな冷静過ぎる意見によってひとまず却下されるのだった。今から考えるとコレって『アンブレイカブル』みたいなスーパー・ヒーロー誕生譚、というかその前日譚というエピソードになってるのだが、この漫画では事態はさらに過去に遡行するって展開を迎え、『Sons』という彼らの少年時代をえんえんと描く大長篇になってしまうのだ。
こうして「スーパー・ヒーローないし正義の味方になれる(可能性のある)主人公というのは、いったいどういう生い立ちで、どういう半生を送れば“主人公の資格”を得ることができるのか?」という問いを、執拗なまでに丁寧に追究することになる――というか、『Sons』は結局、ウィリアムとスティン(J・J)という不憫な兄弟の「息子達」の群像劇となり、彼らの数奇な運命を通して、「父の息子」であることの固有性と、でも誰もが「たかが人間」であること、その逃れがたい因果について、噛んで含めるようにして描き切って、終わる。大長篇となった『Sons』のラストは、再び「現在」のD・Dの堂に入った「お人好しぶり」を描き、さらなる息子・娘達の物語を予感させて(ああ、でもD・D自身が子を持つことはあるんだろうか?)、締めくくられるのだった。で、僕としては、こうして生い立ちまで克明に熟知したD・Dのその後、<ムーン・ライティング>シリーズの続編が、いつか描かれるはずだと思っていた。彼の「なりたくない」正義の味方ぶり――たぶん同僚や親戚の子供達の「愚痴聞き」役が主な仕事だろうけど――の続きや、トマスやドクターら「仲間」との活躍(敵を脱力させるケンカ漫才が必殺技とか?)や、あるいは名のみ登場したマクニール達=ウェアウルフ族のコミュニティーの話や…‥なんかを愉しみにしていたんだけど、残念ながら作者の三原順の早すぎる死によって、もはや自分で空想するしかなくなってしまったのだった…‥。
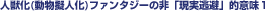
『Sons』時代の少年D・Dは、精神的危機に際してルディという狼男、いや「狼坊や」が主役の空想物語を、絶えず頭の中で考えながら、ニコニコと日常生活を送ろうとする。そのこと自体は、社会性にまつわる一般常識では「現実逃避」と呼ばれるものなので、あまり大っぴらに肯定できることじゃない。ただそれも仕方ないくらいの「精神的危機」ってのはあるのだ(誰でも常に?)。そして三原順の出世作『はみだしっ子』の主役4人がグレアム・ペンギンやらサーニン・アンコウやらアンジー河童やらマックス…はクマだっけ?なんて動物群に化けるように、あるいは『ルーとソロモン』のお化け犬ソロモンがほとんどイジケた人間そのものであるように、彼女の漫画作品の多くには「厄介な自意識を抱えた獣(ケモノ)」としてデフォルメされた人間観=「人獣化」志向があって、<ムーン・ライティング>シリーズはそれらのリアルな深化版でもあると言える。擬人化された動物というファンタジーに仮託されてきた「精神的危機の深さ」の寓意的描写が、『Sons』では「本当に獣(超人)になること」と「緊急避難として獣になる空想をすること」とに峻別され、形而下的(現実的)に突き詰めて描写され、疎外感やアイデンティティー確立の不安という誰にでもあるトラウマの、でも誰とも交換不可能な固有性を持つトラウマの、D・Dの場合におけるサバイバル例として提示されるのだ。トマスの場合はまたちょっと(いい方に?)歪んだ例というかアレだし(笑)、そしてもちろんサバイバルできない場合も往々にしてあるのだ、と『Sons』は語るのだけれど…‥。
|




