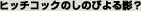 |
フランス映画の話でどうしてヒッチコック?と思うかもしれませんが、間違いではありません。
カルチエ・ラタンのシネマクラブで毎週行われる上映会やシネマテークに集う若者たちは、フリッツ・ラング(『死刑執行人もまた死す』)やロッセリーニ(『イタリア旅行』)などの国外作品に親しみ、“映画の可能性”という点において開眼していったわけですが、当時彼らがナンセンスとした“文芸映画”であり“スタジオ映画”だった今までのフランス映画を否定する一方で、殊に洒落ていて気が利いていて哲学的と傾倒していたのが、なんとアメリカ映画。以外ですよね。中でも【フィルムノワール】の重鎮、ヒッチコックの影響は大きかったようです。
ヒッチコックのストーリーテリングや映像のテクニックは作品ごとに特異かつ天才的。けれど、彼が【ヌーヴェルヴァーグ】に与えた最大の影響は、作品ひとつひとつの完成度というよりも、ヒッチコックという監督が“スタイルを持っている”こと、
“才能をもっている”ことでした。
まだ映画製作に携わる前のトリュフォーは、アンド・レバサン率いる【カイエ デュ シネマ】誌でヒッチコック特集を組みました。当時、映画について語る時、一人の監督について掘り下げることが考えられなかったので、その前代未聞の行為はかなりセンセーショナルで、当然批判されたわけです。そこで彼がいいたかったことは、“これからの映画に求められるのは、ある監督の作品には必ず一貫したその思想が流れていること”つまり、映画には、その監督のアイデンティティーがあるものだということ。これは後に《作家主義》と呼ばれるようになる【ヌーヴェルヴァーグ】のスタンスの伏線だったのです。そしてそれは《フランス映画》に特徴的なスタイルでもありますよね。
こうして、ドメスティックなフランス映画は 、新世界【アメリカ】に触発された若者たちによって、パーソナルな、教訓的な、日常的な《フランス映画》つまり《コンセプチュアルなもの》へと再構築されることになったのです。《フランス映画》を小難しいと感じてしまうのは、そういった作家主義の哲学にあるのかもしれませんね。
既に“ヌーヴェル”ではないといわれる【ヌーヴェルヴァーグ】。それでも、後のポストヌーヴェルヴァーグにしたところで所詮マイナーチェンジでしかなく、今でもフランス的映画観は【ヌーヴェルヴァーグ】の中にあり続けているという事実、その偉大さを認めるしかないでしょう…。 |
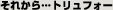 |
さて、10年ほど前のこと、ここ日本で第2次フレンチブームがまき起こりました。ゲンズブールやフランスギャルのキャッチ―なフレンチポップシリーズが次々に再発され、アニエスbを身にまとうプチパリジェンヌが街に出没。そしてこの時、おしゃれなフランスを大いに盛り上げたのも、この【ヌーヴェルヴァーグ】の監督たちでした。このブームがあって、【ヌーヴェルヴァーグ】の監督の名はリアルタイムで知ることのない私たちの中に浸透し、映画好きにもそうでない人にも“ゴダールはお洒落なもの”と認識付けたものでした。
そのゴダールと並び2大巨匠といわれるフランソワ・トリュフォー、『大人は判ってくれない』で世界に著名。その他の作品では『突然炎のごとく』や“アントワーヌ・ドワネルシリーズ”をはじめとする映画史上大きな意味を持つ作品を残しています。監督となってからも評論家肌の人で、映画人のバイブル?ともいわれる著書「映画術ヒッチコック/トリュフォー」(1981晶文者)など、映画論に関する執筆にも意欲的でした。【ヌーヴェルヴァーグ】の旗揚げと成功の両方に大きな功績を残した人です。
【ヌ−ヴェルヴァ−グ】といえばゴダール派という人が多いのかな?とは思いますが、個人的にはゴダールよりもやっぱりトリュフォー。
今ちょうど、《フランソワ・トリュフォー映画祭》も行われていることですし、次回は、『大人は判ってくれない』だけでないトリュフォーについて少し掘り下げてお話ししていくことにしましょう。 |
|
|
 |

