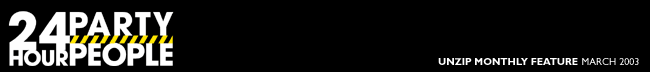
|
||||
|
『24アワー・パーティ・ピープル』や『ウェルカム・トゥ・サラエボ』は実話をもとにしたものだけど、「これが事実の重みなのじゃ」ってな押しつけはなくって、適度なおかしみやルーズさのある空気感に、実は観ていてくつろげさえするところもある。あるいは『日蔭のふたり』や『めぐり逢う大地』は文豪ハーディ原作の文芸大作だけど、純文学の滑稽な程のシリアスさからは自由な感じがある。『バタフライ・キス』や『アイ・ウォント・ユー』なんてのは「殺人」をめぐるサスペンス・ドラマでヒリヒリする焦燥を抱えるキャラクターがいるにも関わらず、どこか呑気な空気も漂ってて、宣伝用に「サイコ・サスペンス」とか「エロチック・サスペンス」とかジャンル名をつけられると、やっぱりどこか苦笑しちゃうようなハズしてる感が生じる。そして『GO
NOW』『いつまでも二人で』『ひかりのまち』が庶民の普通の生活を、時に楽しく、時には苦し気に描写していくのを観て、僕らは(僕は)妙な「連帯感」さえ抱いてしまうし、でも同時に「彼らになり代わってはやれない」という諦めに似た少し醒めた「距離」が、適度に保たれていることにも気づいたりする。――こういう感触を、ズバリ何と言うのか? 「優しい」と言うと甘過ぎるような、「ドライ」と言えば確かにそうだが乾き過ぎてはいない、この映像と音楽の「肌触り」。その独特の癖になる感触を、うまく言えない。 ただ、冬の底に立っている者の、凛としたユーモアというか明るい覚悟というか、そんな「気配」がある。その者が仮に天使だとして、彼が見つめるダメダメな人達や非運な人々、楽天的に転がる連中や社会からハミ出してしまう「孤児」までも含む人間達は、自分達がじっくり見つめられ、観察されている気配を、感じてはいるのかもしれない。でも、その視線は彼らを鋭く責めているものでも、逆に今にも手を差し伸べようと甘やかすように見守っているのでもない。確かに傍観者の視線ではあるのだが、盗み見の不快さはあんまりない(というか盗み見しているのは僕ら観客だったりする?)。逆に、見ていてもらって、まんざらでもない気分になるような、そんな感触の視線なのだ。いや、世界中の古今の映画の中には、声高に主張する必要のある視線も、絶望的な視線も、暴力的なのもファンキーなのも、シニカルなのも甘美でナルシスティックなのも、訳知り顔の視線なんてのもあるし、それぞれの美点も悪い所もあるから、何も「彼」の視線だけが正しいってわけじゃあない。でも、そういうのもあるってことの、何とも言えない安心感が、マイケル・ウィンターボトム監督の映画を観ている時の感触、肌触りに、一番近いような気がするのだ。そういうわけで、僕は彼の名前と彼の作品が、わりと好きだったりするのである。 Text:梶浦秀麿 [もう少しまともな論考を書け!という人には…‥] ――マイケル・ウィンターボトム監督についてのささやかな論考、続。あるいは蛇足ないしゴタク? |
||||
|


