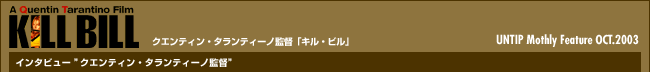|
 Q:「キル・ビル」の構想は、何年も前からあったとうかがっています。どんないきさつがあったのですか? Q:「キル・ビル」の構想は、何年も前からあったとうかがっています。どんないきさつがあったのですか?
A:最初に構想を思いついたのは、「パルプ・フィクション」を撮っていた時。いつものように、撮影が終わってスタッフと飲みに行こうと、一度家に帰って着替えていたら、突然、頭の中に、「復讐に燃える女殺人鬼」というアイデアが浮かんだ。待ち合わせのバーに着いてすぐ、ユマ・サーマンに「君の次の役を思いついたよ!」と、このアイデアを説明すると、彼女は「クールだわ」と、とても喜んだ。その後、彼女もどんどん自分が演じる役について意見を出してきたよ。このキャラクターが最初に殺される時、ウエディングドレスを着ていることにしたら、と提案したのもユマなんだ。
Q:今回の「ボリューム1」の、主な舞台は日本です。美術監督には種田陽平氏を雇われましたが、日本という背景を描くことに、どんなふうに気を使われたのでしょうか?
A:日本を適当に描いてきたハリウッド映画はたくさんあるけど、僕は絶対それはやりたくなかった。だから、美術監督と衣装デザイナーは、一番気を使って選んだんだ。種田氏は、僕がこれまで出会った中で、最高のアーティストと言える。細かいところまで、さりげないこだわりがあるんだ。彼が作ったセットは、毎日現場で目にするが、いざカメラを回し始めて、俳優に焦点を当てた時に、その背後にあるとても小さなデコレーションに気がつくことがある。主張しすぎないそれらの小さな「何か」が、映像にユニークさをもたら
してくれるんだ。感服したよ。
Q:今回の映画も、バイオレンスがかなりあります。映画のバイオレンスを批判する人も多いですが、あなたの言い分は?
A:僕にとって、バイオレンスはシネマという娯楽の一部。シネマという世界の中で、フィルムメーカーが思いきりやりたいことをやれる、そのひとつがバイオレンスなんだ。文学、絵画、舞台、他のどのフォーマットでもできない。映画だから可能なことなんだ。
Q:バイオレンスが理由で、「キル・ビル」も、欧米では私たちが見るのとは違うバージョンが公開されるそうですね。
A:日本人は、マンガやTVを通して、バイオレンスを娯楽としてとらえることに慣れている。だからいちいち目をつりあげず、笑って見られる余裕がある。だから、僕は日本向けに、特別にこのバージョンを作った。こんなことが出来て、僕はフィルムメーカーとしてすごくラッキーだと思うよ。
Text:猿渡由紀 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|