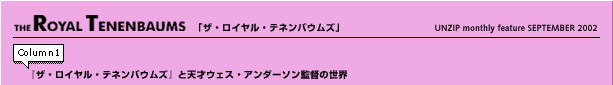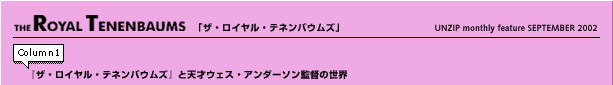小学校の教室で、授業中ウロウロしたりする落ち着きのない子供のことを、最近では多動性障害とかADHD(だったか?)とか集中力散漫症とか集中力失調障害とかなんとか言うらしい。ウェス・アンダーソンの映画の登場人物についてじっくり考えてみると、みんなこの症状に陥っているようにも思える。このもどかしい感じ、自分の才能が認められない、とか、才能が認められても不全感がつきまとって、結局もがき続けてしまう人々の世界。これって若い生意気な連中、言ってみれば天才ワナビーズ、自称アーティストの根拠のない自信をペロリと剥いた時の不安だったり、アーティスティックなタレント(才能)を模索するもがき、だったりするのと通底しているのかもしれん。「天才」とか語られつつ、その天才の「天才ぶり」は表面的にしか語られず、コアになるのは満たされない感じ。そういうのを抱えた若者(あるいは中年もか!)の気分を代弁してるって捉え方もアリかもしれないのだ。つまり自意識過剰な多動性障害じみた「やりたいことあり過ぎるけど何で成功できるかわからんっ」系(笑)の若者達を、この映画は「わかる、わかるよ、みんなそうさ」ってな感じで甘やかす応援歌なのかもしれないのだ。だって好きな作家がサリンジャーだよ、おい。
↑なんて、昔「サリンジャーを正しく葬り去ること」(青土社『聖母のいない国』所収)を書いた小野谷敦に、ムキになって反論した僕なのに(→コラムstageP参照)、そのサリンジャーの影響を公言し、観客側には庄司薫や村上春樹の系譜の延長線上にあるとも捉え得るウェス・アンダーソンなのに、どうもなんか皮肉入ってしまってるのは、何故かしら(笑)。やはり同族嫌悪というか嫉妬なのかなあ……。でも映画という世界にディープにはまっている人達からこうも支持されるって状況は、なんか含みがあるような気がする僕なのだった。
ちょっと映画に深入りしてみよう。例えばこんな場面----「離婚するの?」「私達のせい?」「確かに子育ては重荷だったが、私に誠実さが欠けたのかも……」----別居宣告時の子供達とロイヤルの台詞はこうだった。子供達は当時マーゴ12歳、チャス11歳、リッチー10歳(のはず。映画内では語られていないが情報を整理して推測。僕はこう読んだんだけど論証は長くなるのでまた別のところで)。ここで、この「誠実さ」ってのは女絡みかぁとつい思っちゃうし、22年後のロイヤルも「確かに浮気はしたが」とか何度か言ってるので、原因は彼の浮気性かな、と曖昧ながら誰もが思うように編集されてるんだけど……。映画を冒頭からぼんやり観ていると、別居後に母エセルの「英才教育」が始まったかにみえる。けど別居宣告時にすでに子供達は天才を発揮していたってのが服装でわかる(倒置された語りだったワケだ)。だから別居の真の原因は……これもまたちょっとしっかり観てればわかるはず(というか例えば香山リカは週刊朝日の映画評でしっかりネタバラシしてたし)。そして問題はここからなのだ。思い出して欲しい。この映画は「ロイヤル・テネンバウム氏の35歳から68歳までのライフ・ストーリー」だと僕が書いていたことを。そう、これは何より彼の話なのである。
ロイヤルが家族との再会を画策したのは、「ホテルを追い出されたから」だとか「別居するだけで何人かの求婚を断ってきたはずの妻エセルが結婚するかもしれないから」とかいうハッキリしない理由ではない。実は、その「真の原因」に対する彼自身の“復讐に似たもの”の決着をつけるため、なのだ。つまり「家族の再生」なんて映画の主題的におさまりのいい事態というのは、ただ彼の「エゴの達成」によって何となくもたらされてしまうってな話なのである。だから妻の再婚を妨害するはずなのにあっさり認めるのも、リッチーの自殺未遂やマーゴの浮気(やミドルネーム)やチャスのBB弾の恨みなどへの対応のあやふやで不確実な感触も、「彼が家族を大切に思っているから」なんてことではちっともなくて、ただ自分の名誉の問題でしかない。この、なんて自分勝手な、最後まで自分勝手な人間、そしてその哀しさ……。文字通り「墓標銘を用意してから、そのつじつまを合わせるためだけに成されたかのようなエゴイズム」こそ、この映画のダークサイドにしてコアなのだ、と僕は思う。だけど、映画はなんだか憎めないいい人に見えるようにロイヤルを描き、巻き込まれる家族達も細部までゴチャゴチャと描かれて、映画の終わりには家族達と一緒になんだかうっかり感動までしてしまうように作りこまれている。だから、トンガリ系の映画評論家はみんな「何だかよくわからないけど、いったいどこに感動しているのか判らないけど」などと言いつつ、この映画に賛辞を惜しまないってな現象が起きてしまうのだ。
「……(前略)『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』を見て、映画というもの自体に誇りを感じた。最後には泣きたくなっちゃった。これほど好きになれる映画があるなんて、感動的だったから」----プレミア10月号「私の人生を変えた映画」特集中の、クリスティーナ・リッチ発言より
この映画の「面白がり方」として提示してみた「ロイヤル=悪気のない極悪人」説なんだけど、これって要は仏教の「悪人正機説」(by親鸞)の現代アメリカ版ってことだったりする。善人でさえ成仏できるのに「いわんや」悪人が成仏できないわけないじゃんってヤツ(というか親鸞は「自力成仏できる善人なんておらへん、ひとはみな愚かな悪人なんじゃ、にも関わらずみな成仏できるから仏ってのはありがたい」って言ってるんだけどさ)。この映画でよく比較されるサリンジャーの<グラース家>サーガが、当時の禅仏教のアメリカ(キリスト教)化かつ文学的普及版だったことを想起しよう。『フラニーとゾーイ』でのその描き方に対して、小野谷敦は「宗教理解の浅薄、社会性の欠如(非社会性)」という点から痛烈に批判してみせたのだけれど、浅はかで結構、というか、この浅はかなレベルでさえ僕らは上手く言葉にできないものなのだ。だからサリンジャーの子供達のひとりであるウェス・アンダーソンの描く一冊の書物について、「なんかいいね」というしかないし、頭の方で書いたように、あらすじを言葉で説明してもピンとこなかったりするのもムベなるかなってことなのだ。つーわけで、親鸞上人の教えをアメリカナイズすると、「やっぱ死んだらお墓参りしてほしいじゃん、家族にさぁ」ってな、ある側面では酷いエゴイズムなんだけど、それが現代人の「救い」の表現なのだと、トボケた筆致で描いてみせたウェス・アンダーソンは、実に立派にサリンジャーの衣鉢を継いでいるのである。
前作『天才マックスの世界』がサリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』と比較され、『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』はサリンジャーの短篇群<グラース家>サーガと比較されることから、以上のような「読み方」をデッチアゲ……もとい提案してみた。この映画をより愉しむための参考になれば、と思う。ちなみに『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』は、オーソン・ウェルズ『偉大なるアンバーソン家』とかPTAことポール・トーマス・アンダーソン『マグノリア』(編集のディラン・ティシュナーが本作にも参加しているし)とかとも比べられている。最近作だともっと新人のデビュー作『ドニー・ダーコ』と比較されたり(SFマガジン10月号の映画欄のように『ドニー・ダーコ』は『CQ』と並べるってのが正解かも)している。『ズーランダー』と並べてる雑誌もある。これはキャスト人脈的には非常に正しい。----ってなワケで、最後にウェス・アンダーソンの略歴なんてのを紹介して終わることにしよう。(4/5)
→次ページへ |
|
|
|