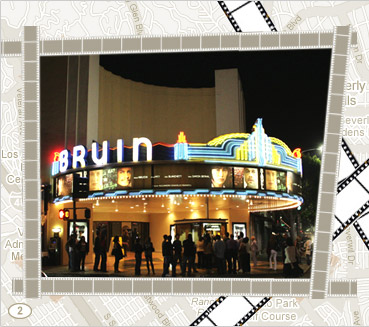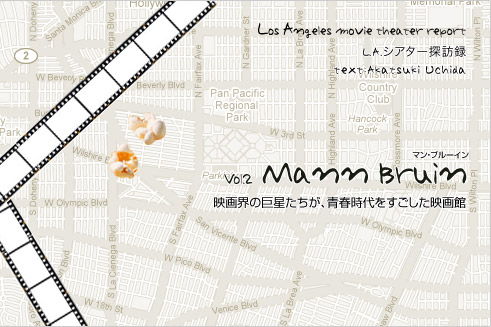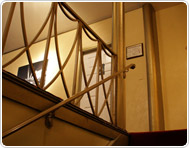先にも述べたとおりこの『BABEL』(バベル)は、キャストの顔ぶれや評判の割には、観客動員数的に地味な作品である。何しろ、公開週(10月27日公開)は全米ではなく、LAやNYなどの一部都市のみの公開。3週目にしてようやく興行成績トップ10に顔を出したというスロースタートっぷりである。だが、著名映画評論家たちが高く評価していたことが功を奏したか口コミで徐々に評判を上げ、わたしが映画館を訪れた4週目の土曜日には、かなりの人数が客席を埋めていた(恐らく300〜400人)。観客の顔ぶれ的には、当然のごとく学生らしき若者が大半を占めていたが、通常以上に年配者たちの姿も多く見られたように思う。
本当のことを言うと、わたしがこの映画を観たいと思った最大の理由は、役所広司や菊池凛子といった日本人俳優が出演していたからである。だが実際に観てみると、「この映画を観る場所として、南カリフォルニア以上に適切な場所は無い!」と、LAにて同作を観られた僥倖[ぎょうこう]を嬉しく思った。特に、南カリフォルニアにて暮らす日本人であるわたしには、あらゆる方面で自己の体験や経験とリンクする部分が多かったのだ。
相互不理解の象徴である“バベルの塔”の名にちなんだこの作品は、言語や文化の差異により生じる意志の齟齬[そご]、排他的思想、先入観、偏見などのテーマを、異なる4つの国を舞台に、多角的に深く抉[えぐ]っている。
舞台のひとつは、モロッコ。山岳地帯で山羊を飼育し生計を立てる一家は、ジャッカルの脅威から山羊を護るため一丁のライフルを購入し、そのライフルを山羊番である二人の息子に託す。幼い少年たちは、ライフルの性能を試してみたいという好奇心から、遥か眼下を走るツアーバスに向けて発砲するが、不幸にもその銃弾は、旅行中のアメリカ人女性(ケイト・ブランシェット)に当たってしまうのだった。
襲撃された女性の夫(ブラッド・ピット)は、一刻も早く妻を病院に連れて行きたい一心で奔走するも、言葉も文化も国家システムも異なる地では全てが思い通りに進まず、苛立ちと焦燥感、そして絶望感を募らせていく。その一方で、自分たちの軽はずみな行為が人命を脅かしてしまった事実に、ゴート飼いの少年たちは驚き、焦り、後悔し、そしてその事実を知った父親は悲嘆にくれる。
ときを同じくし、サンディエゴ(最もメキシコとの国境に近い都市)にある件のアメリカ人夫婦の家では、夫婦の留守を預かり二人の子供の面倒を見ているメキシコ人のベビーシッターが、窮地に立たされていた。愛する一人息子の挙式が迫っているのに、雇い主夫妻は帰ってこないからだ。悩んだ挙句にベビーシッターは、預かっている子供二人を連れてメキシコへと戻り、結婚式に参加することを決意する。
これら先述の3つの挿話には明確な相関関係が見られるのだが、それらとやや独立して存在するのが、東京のエピソードだ。東京で展開される物語は、反抗期/思春期を迎えた聾唖[ろうあ]の女子高校生が、父親や世間そのものへの反発心を募らせる様が描かれている。ただでさえ難しい年頃、そして聾唖という過酷な状況に加え、彼女は母親が自殺したという悲劇的な過去まで抱えている。それでも少女は、同じく聾唖の友人たちと高校生活を満喫しているかのように見え、他の同世代の女の子たちと同じように異性への興味も示していく。だが、周囲に多くの人がいることで、逆説的に証明される自身の孤独。光と人と雑踏が沸き返る街中を、ただひとり音のない世界として彷徨する少女の孤立感や渇望は、東京の喧騒を知っている者にとってあまりに痛すぎる。
ちなみに、この聾唖の少女を演じる菊池凛子の存在感は名優揃いの今作中でも際立っており、多くの批評家たちも「抜群の演技力」「美しい」と絶賛。早くも、オスカーの助演女優賞へのノミネートが確実視されているほどだ。(ただ、アメリカ人の目にはともかく、同じ日本人の自分にとって、当年24歳の菊池が“女子高生”というのはかなりムリがある……と感じたことだけ加えておく)
そして、やはり南カリフォルニアの人たちにとって最も身近に感じられたエピソードは、サンディエゴからメキシコに渡るベビーシッターのそれだろう。恐らく皆さんも想像がつくように、本作は現代社会の問題点に焦点を当てており、見た者の胸に痛みを与える作品である。だが、ところどころにウィットの効いたセリフなどが散りばめられており、客席から笑いが起きることもしばしば。その中でも最も大きな笑いが巻き起こったのが、アメリカ人の子供二人を連れたベビーシッターが、彼女の甥とともに車でメキシコへの国境を越えた場面でのやり取りだろう。
突如として変化した周囲の景色や空気に、子供の一人が「ここはどこ?」とたずねる。帰ってきた「メキシコだよ」という返事に、少年は「ボクのママは、メキシコは危険な場所だって言ってたよ」と何の罪悪感もなく答えるのだが、その言葉を聞いた甥は「何しろ、メキシコ人だらけだからな!」と、陽気に返すのだ。
この一連の会話がなぜ笑いを誘うのか――恐らくアメリカやメキシコ以外の地に住む人たちには、ピンと来ないだろう。だがこの手のジョークは、アメリカ、特に国境に近い都市ではすでに定番となっているものであり、また、アメリカ・メキシコ両国の人にとって自虐的な冗談なのである。
ロサンゼルスやサンディエゴなどの都市では、レストランやスーパーの従業員の大半は、メキシコ人である。そもそもロサンゼルスやサンディエゴにおける人口の半数近くはヒスパニックであり、その大多数は重要な労働力であるのだから、この両都市はメキシコからの移民(例えそれが合法であれ違法であれ)無しには機能しないのが現実なのだ。映画内でも、おそらく中流以上に座しているであろうブラピ&ケイト夫妻も、メキシコ人(違法移民)の女性をベビーシッターとして雇っているのだから。
このベビーシッターの女性と雇用者のアメリカ人夫妻、そして子供たちの関係は至って良好に見える。夫婦は、子供を預けて長期旅行に出かけるほどに彼女のことを信頼しているし、子供たちも彼女のことを慕っている。もちろんベビーシッターも、実の親もかくやという深い愛情を子供たちに注いでいる。また、ベビーシッターは子供たちにスペイン語で語りかけ、子供たちはその言葉を理解し英語で返すのだが、このような光景は、実際にサンディエゴに行くと普通に目にする日常だ。個人レベルでは、アメリカ人とメキシコ人の間に垣根など存在しないように見える。
だがその一方で、ケイト演じる母親は、子供たちに「メキシコは危険なところだ」と教えているのである。恐らくは、何の悪気や意図もなしに。これもまた、今日のロサンゼルスやサンディエゴの、リアルな姿である。そしてそのような状況には、メキシコ人もアメリカ人も、お互い自嘲気味に笑うしかないのだ。アメリカ人は、メキシコ人を労働力として頼っており、そして個人レベルでは良好な関係を築いているにも関わらず、それでもどこかでメキシコ人を卑下するような自分たちの矛盾した態度に。そしてメキシコ人は、アメリカに順応し貢献しているという自負もありながらも、未だにアメリカ人から批判的な目を向けられることがあり、そして自分たちもどこかで引け目を感じているという事実に……。いずれにしても南カリフォルニアに暮らす人々にとって、先述のようなジョークに対し眉をひそめたり触れることを避けたりするような段階は、とうに過ぎている。あまりに身近すぎる話題であるからこそ、あまりに生活の一部として定着しすぎているからこそ、思わず可笑しくて笑ってしまうのだ。
一連の“メキシコ・ジョーク”で起きた笑いは、「生まれた環境や操る言葉が違うし、そもそも他人なのだから、理解できない部分があるのは当然だ」という諦念[ていねん]の産物といえるだろう。だがその諦念は、同時に「どんなに文化や価値観が異なっても、同じ人間なのだからどこかで理解しあえるはず」という希望と表裏一体でもある。
この『BABEL』(バベル)の登場人物たちのもとには、次から次へと、それこそ不運のドミノ倒しのごとく辛い出来事が降りかかり、観ている側としては「もう勘弁してくれ!」と叫びたくなるほどだ。だが映画を観終わった後、散々痛めつけられたはずの心に、ポッと優しく温かい想いが燈る。
それは最後、人間関係のネガティブ要素に埋め尽くされていたこの作品が、「それでも、お互い理解できるはずだ」という希望の側に帰着するからだ。